| No.58 2009年4月 |
- 2019年
- №199 シロチドリ
- №198 マガン
- №197 ムギマキ
- №196 アカガシラサギ
- №195 コミミズク
- №194 ツメナガセキレイ
- №193 コジュリン
- №192 オグロシギ
- №191 ツメナガセキレイ
- №190 シジュウカラ
- №189 シロカモメ
- №188 チュウシャクシギ
- 2018年
- 2017年 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 『郷土はとがや』より
- 鳩ヶ谷の生物
New! 鳩ヶ谷郷土史会会報 『嫌われもの「カワウ」とその仲間』
鳩ヶ谷で見られる野鳥シリーズ (71)
モズ(モズ科) Lanius bucephalus
 |
| 小枝に止まるモズの雄 |
|---|
芝川の土手に繁茂していた雑草の刈り取りが始まると、待っていたかのように近くの木の枝や棒杭に止まって、長い尾をゆっくり回しながら、鋭い目で獲物を探しているモズの姿を見かけます。いざ、獲物を見つけるとパット飛び立ち昆虫類や小動物を捉えてきます。河原ではセスジツユムシ、アマガエル、カナヘビなどが餌食になります。以前に水田の棒杭に止まっていたモズがペリット(不消化物)を吐き出したので、そのあたりを探したところ100個ほどのペリットが落ちていました。分析してみると中味は全てイナゴでした。モズはハヤニエを作る習性がありますが多種多様な生物が餌食になっています。繁殖期は他の小鳥と異なり、3月頃が繁殖期で4月中旬頃には巣立ち雛が見られるようになります。鳩ヶ谷市内で繁殖する個体は少なくなりましたが、秋になるとテレビのアンテナや高い木の頂で高鳴きをするので存在がわかります。この声を聞くとそろそろ冬かなという感じがします。
自然の記録:
4月 1日 今日はあいにくの雨となり肌寒い日でしたが、早朝からウグイスが囀り、庭のソメイヨシノが1部咲きとなりました。
4月 2日 朝からかなりの強風が吹いていましたが、市内のサクラは2~3分咲きとなりました。八幡木中学校の正門付近では7~8分咲きになっていました。
八幡木1丁目の空き地ではタンポポが盛りでセイヨウタンポポ1株、交雑タンポポ20株が開花していました。
八幡木中学校脇の毛長川ではカルガモ(3羽)、調節池付近ではコガモ(雄6雌2羽)、ハシビロガモの雌雄が泳いでいました。また、上空をアオサギの成鳥が風に煽られるようにして飛んでいきました。
庭ではキュウリグサ、タチイヌノフグリやオランダミミナグサが開花しました。
4月 3日 本町3丁目付近の江川沿いでキチョウが飛んでいました。見沼代用水沿いはサクラが7分咲き、ムラサキケマンが数カ所で開花していました。
家の庭ではマルガタゴミムシやビロードツリアブなどが初認です。
4月 5日 坂下町2丁目(浅間橋付近)の見沼代用水沿いでカントウタンポポ50株、交雑タンポポ1株が咲いていました。サクラは何処も満開となり花見の人たちが多く賑やかでした。
今年も庭のニリンソウが一株花をつけました。これから順番に花芽をつけることでしょう。
4月 6日 屎尿処理センター付近の芝川でカルガモ(5羽)、ヒドリガモ(雄29、雌31)、に混じって鳩ヶ谷市初記録となるアメリカヒドリ(113種目)雄が記録されました。目の後ろの緑色は大分薄くなっていましたが、おでこの白は奇麗でした。
オオジュリンも僅かな葦陰で採餌していました。今日は一日中暖かく芝川土手沿いのサクラは何処も満開状態となり、桜の花にはヒヨドリやスズメが群れていました。土手にはツクシが所狭しと伸び放題です。イタドリの赤紫の若葉も出てきました。若葉は食べることができますが、食べ過ぎると良くないようです。モンキチョウ、モンシロチョウ、ベニシジミ、キタテハ等も飛んでいました。
17時30分頃、本町にある御獄神社のイチョウの木に10羽のオナガが飛来しました。
 |
 |
| アメリカヒドリ雄 | サクラを啄むスズメ |
|---|
 |
 |
| イタドリの若葉 | ゲンペイコギクの小群落 |
|---|
4月 7日 桜町6丁目の路上をツマグロヒョウモンの幼虫が歩いていました。今年初記録です。
庭のヒゴスミレの鉢に入れておきましたが、しばらくしてみると姿が見えませんでした。その代わりにカナヘビが中から出てきたので、もしかすると餌食になったのでは?
4月 8日 桜町3丁目の落合公園付近ではカントウタンポポ16株、交雑タンポポ15株、ムラサキケマン、桜町6丁目12付近では交雑タンポポ11株が優占していました。庭ではハルジオンが開花しました。
4月 9日 今年初認のツマキチョウが庭を飛んでいました。キチョウやモンシロチョウも、クコの新芽ではヒメカメノコテントウ、ニジュウヤホシテントウ、ナミテントウなどが集まっていました。ムナグロナガハムシ幼虫数匹と成虫も数匹出現し、交接しているものもいました。
4月11日 一日中暖かく、ナミアゲハ、スジグロシロチョウ、モンシロチョウが庭に飛来し、レンギョウの根元近くでツチカメムシが10匹ほど歩き回っていました。本町2丁目の樹林脇ではドウダンツツジ、ヤマブキ、クサイチゴ等が満開となりました。
4月13日 ホソヘリカメムシ、ハラナガツチバチ、アシナガグモなどが庭を徘徊し、オナガがよく鳴いていました。八幡木の幼稚園の林でもオナガの群れが飛んでいましたが、そろそろ繁殖にはいることでしょう。また、自宅付近の上空をアオサギが飛翔。
4月14日 辻バス停前の水田でレンゲが満開となりました。市内でレンゲを見ることができる場所は少なくなりました。コンフォール東鳩ヶ谷の路肩では、ナガミノヒナゲシ、カラスノエンドウ、タンポポ類、オオジシバリ等が満開です。
13時頃、自宅上空をカルガモが通過しました。
市内のタンポポ調査
| 観察場所 | セイヨウタンポポ | カントウタンポポ | 交雑タンポポ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 桜町3丁目 | 0 | 16 | 15 | 31 |
| 桜町4丁目 | 0 | 19 | 11 | 30 |
| 里中学校付近 | 0 | 15 | 80 | 95 |
| 桜町6丁目 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 本町2丁目 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 坂下町2丁目 | 0 | 50 | 1 | 51 |
| 八幡木1丁目 | 1 | 0 | 20 | 21 |
| 合 計 | 1 | 100 | 146 | 247 |
4月16日 青少年会館1階軒下でツバメが古巣を修理中、今年も繁殖に入りそうです(2年目)。
ゴミ箱の中でアオオサムシが蛾の幼虫を捕らえて食べていましたが、殆ど食べ尽くす寸前であったため種類がわかりませんでした。土の中からコガネムシの仲間の幼虫が1匹、腐葉土を作っていたビニール袋の中でカブトムシの幼虫が死んでおりシロカビまみれになっていました。今年初めてのクロアゲハも飛来しました。クロアゲハは昨日上野動物園で飛んでいるのを確認したばかりでした。
グリーンセンターの園芸植物売り場では、ツマグロヒョウモンが飛んでいましたので、市内でも見られるようになるでしょう。
4月20日 アオオサムシ3頭、マルガタゴミムシ、ヤスデ、コウガイビル等がゴミ箱を移動したところ、土の中に潜り込むようにしていました。庭ではハハコグサ、ハルジオン、キケマン、ムラサキハナナ、カキドオシ、シャガ等が満開となり、足の踏み場もないくらいに蔓延っています。
4月21日 コンクリートの溝の中にアオオサムシ、センチコガネ、ゴモクムシの仲間、等の遺骸が落ちていました。また、壁際の蜘蛛の巣にはアオオサムシの乾燥した遺骸がありました。
4月22日 ルリタテハ、ヤマトシジミ、ナミアゲハが庭を飛び回り、シデムシやアオオサムシが交接、それらの昆虫を狙ってカナヘビが走り回っていました。狭い庭でも弱肉強食の世界があります。ハルノノゲシやタンポポの花の間をホソヒラタアブが飛び回っていました。全国的にミツバチが減少しているようですが、我が家の庭でも例年に比べ少ない気がします。
ホオズキの若葉ではホオズキカメムシが交接しており、いずれ沢山のカメムシが出てくることでしょう。
4月24日 昨日とは一転して気温が下がり、肌寒い一日であった。ブロック塀に羽化したてのホシホウジャクが止まっていましたが、30分後にはいなくなりました。無事に飛び立ったのでしょう。
4月26日 庭の片隅にオニノゲシが1株伸びてきました。毎日歩いている所以外は草が生え、現在開花中の植物は、交雑タンポポ、ハルノノゲシ、ハハコグサ、チチコグサモドキ、ハコベ、キケマン、カキドオシ、カラスビシャク、ニリンソウ、カタバミ、キュウリグサ、ゲンペイコギク(ペラペラヨメナ)、コナスビ、コバノタツナミ、ムラサキハナナ、ヤエムグラ、など、下線のある植物は、いつの間にか侵入した植物です。まだ開花はしていませんが、ボタンクサギも10本ほど生育してきました。ゲンペイヨメナの花は白色ですが、枯れる頃になると薄いピンク色になるところから源平(源氏と平家)の白と赤を表していると言うところから名付けられたと言われています。
若い葉が伸びてきたクズの蔓にはマルカメムシの30匹以上の集団が見られるようになりました。
4月27日 桜町5~6丁目付近を散策したところ、オオジシバリやホウチャクソウの群落、そして2株ではあるがエビネを見つけました。エビネはホウチャクソウの群落の中にあったので見過ごすところでした。ウラシマソウも数カ所で見つかりました。
6丁目ではツツジが満開になりました。また、某所ではスダジイの古木に竹が侵入し、幹を支えた格好になっています。
中央病院の敷地内でコミスジ、我が家の庭でアオスジアゲハが今年の初記録です。
中央病院の敷地内の林の中で、ツグミが4羽忙しく飛び回っていました。そろそろ渡去するのでしょうか。今年はツグミの美しい囀りを聞いていません。
夜になり久々に部屋の壁をヤモリが徘徊、元気で冬を越したようです。
 |
 |
 |
| 6丁目のツツジ | スダジイの古木 | ホウチャクソウとドクダミ |
|---|
4月28日 何処から来たのか解りませんが、庭のピラカンサの枝にツマグロヒョウモンの終齢幼虫がいました。朝から夕方まで同じ位置から全く動いていないので、蛹になる準備に入ったようです。ここ数日ササグモが急に増加したようです。小さめの個体が多いので何処かで孵ったのでしょう。
鳩ヶ谷から消えた生物・消えつつある生物 22
カラスビシャク
 |
カラスビシャクはサトイモ科の植物で、蛇の枕、狐の蝋燭あるいは半夏、等とも呼ばれています。カラスビシャクには細長い頭巾型の花が咲き仏炎包と呼ばれています。仏炎包とは仏像の背後にある炎形の装飾(光背)で、それに似ていると言うことから名が付けられています。この仏炎包を柄杓にみたて、人のものよりも小さいということからカラスの名が付いたといわれています。
カラスビシャクは畑の雑草と言われて、以前は何処にでも生えていましたが近年では見られる場所が限られてきました。
子供の頃は、キツネノカミソリと同じように墓地によく生えていたのでお墓の植物と思っていました。この仲間には、ウラシマソウ、マムシグサ、テンナンショウあるいはユキモチソウなどがあります。
この植物の根茎は半夏と呼ばれ、漢方薬として催吐作用、鎮静作用、鎮咳作用、利尿作用唾液分泌促進作用、等の薬理作用が知られています。
半夏と名前のよく似た植物にハンゲショウ(半夏生・半化粧・カタしろグサ)がありますが、全く別の植物です。
我が家の庭でも、例年数株が生育してきます。通常の花期は5月~8月ですが、今年は4月20日には開花しました。
地球温暖化を考える(14)
オーストラリアの湿地帯の乾燥化
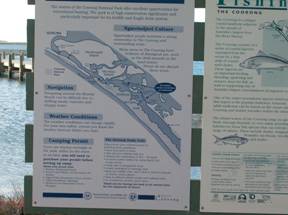 |
 |
| 乾燥が進行している湿地帯 | |
|---|---|
アデレード(オーストラリア南部)近郊のマレー川河口保護区の乾燥について、No.55号で報告しましたが、写真を整理していたところ乾燥地帯の高空写真が見つかりました。淡色に見えるのが乾燥化が進行している部分、薄緑色に見える部分が湿地帯の水域です。全体的に乾燥化が進行しているのがよく解ります。
マレー川流域では、オーストラリアの農産物の約30%が生産されていると言われており、その一部は日本へも輸入されています。過去150年の間に川の周辺に沿って酪農地が広がるにつれて、川からの水の汲み上げが量が増加すると共に、川の水量が減少してきたため、川や湿地帯の存続が危ぶまれる状況になっていますと現地ガイドが説明していました。
マレー川は州都アデレードの南東に注ぎ込んでおり、河口の水が減るという事は、アデレード市の水源の減少を意味します。過去にも、河口の水量が減少し、海水が川を250kmもさかのぼって来るという大惨事が起きています。 しかし今では、1940年に河口近くにつくられた5つの堰のお陰で、河口手前の湖で淡水が確保されるようになり、アデレード市民の生活やその周辺に広がる酪農地も、海水の危機にさらされる事は無くなりました。しかし、淡水がなくなることは、もっと深刻な事態になる可能性があります。日本の食糧事情にも大きな影響を与える可能性もあるのですから。
